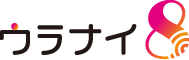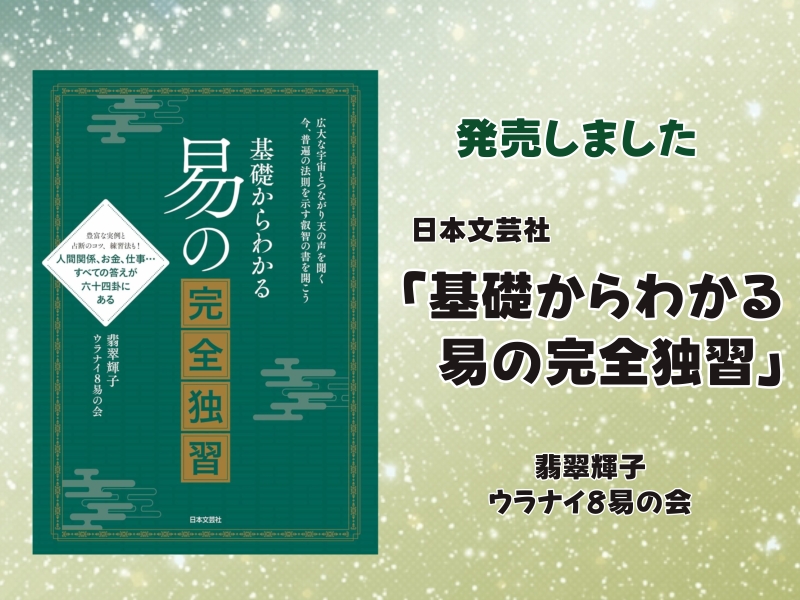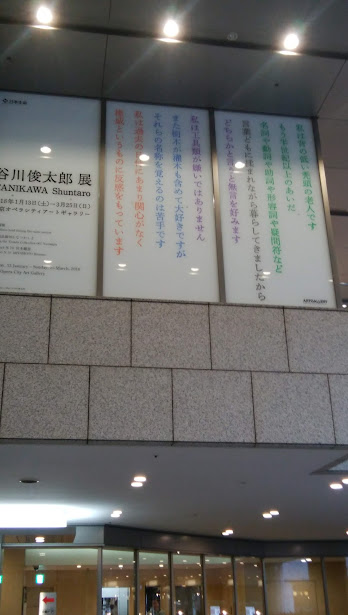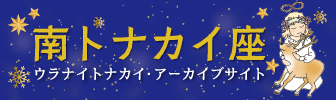みなさま、おはようございます。
スペイン巡礼中の翡翠先生のお留守を預かる「開運招き猫ーず」おかげさまで四週目です。
今週は、立田アカツキ(たつたあかつき)さんが担当します。アカツキさんは、長らくハンドルネーム「暁」さんとして活動されていましたが、苗字をつけて「立田アカツキ」さんに変身&パワーアップなさっています。
◎ これまでの記事はこちら →★
今日の話題は、なーんと「呪文」です。占いをするには不可欠な「象徴」の世界、みなさんも大好物ですよね。「ことだま」と言われるように、言葉とイメージと呪文の不思議な世界について、アカツキさんが熱く語ってくださいます。
それではいってみよう!(天海玉紀)
*** *** ***
占い愛好家の立田アカツキと申します。
占いの勉強が大好きで、西洋占星術や算命学や易などの講座を受けたり、本を読んだりして楽しんでいますが、思えば子供のころから、神話とか魔法使いとかそういう世界が大好きでした。
思春期の頃はルネ・ヴァンダール先生の『魔女っ子入門』や占い雑誌を読み、おまじないにも凝り、「最新恋のおまじない100」みたいなムック本を買ったりもしました。
ある時、そんなおまじない本の中の「魔法の呪文」を集めたコーナーに『メリー・ポピンズに出てくる呪文』として「スーパーカリフラジリスティックエクスペリアスドーシャス!!」が載っていたのです。
「メアリー・ポピンズ」シリーズは有名なイギリス児童文学ですが、この「スーパーカリフラジリ…」というフレーズは原作小説には登場しません。
原作「メアリー・ポピンズ」シリーズにはイギリスの古典の登場人物や空想上の動物たちが現れてメアリー・ポピンズや子供たちと会話したり騒動を起こしたりしますが、1964年にディズニーが製作した映画版「メリー・ポピンズ」ではその色は薄く、不思議な力をもつナニー、メリー・ポピンズと子供たちのゆかいなミュージカル、といった感じ。
その映画の中で「のぞみをかなえてくださることば」として「スーパーカリフラジリスティックエクスペリアスドーシャス!!」の歌が歌われるのです。
「スーパーカリフラジリスティックエクスペリアスドーシャス!!」は1964年にアメリカで作られた曲の歌詞&タイトルであって、そこに不思議な力なんか存在しないんじゃないか?と当時そのムック本を読んだ私は違和感を感じたんですよね。
「スーパーカリフラジリ…」というのは、映画製作以前からアメリカで言葉遊びとして広く知られていたフレーズだったそうで、似たようなタイトルの曲が他にもあるようですが、それにしたって1940~50年代とかなので、そんなに古いものではない。
宗教とか神話とか、あるいは何百年も信じられてきた民間信仰的なそういう裏付けがないと、「おまじない」「呪文」とはいえないんじゃないかと。
しかし、おまじないだって「彼から電話がかかってくるおまじない」なんて、電話が発明される以前にはなかったはずです。
手紙、電話、FAX、メール、と伝達手段が増えていくにしたがって、それにまつわるおまじないも生まれる。
陰陽師を題材にしたフィクションでは、「急急如律令」という呪文を唱えて式神を操ったり結界を張ったり、という描写がよくありますが、そもそもの言葉の意味は「急々に律令(法律)の如くに行え」というもので、古代の中国の行政文書に書かれた言葉でした。
つまり、お役所の書類文言だったのですが、それが日本に入ってきて、やがて呪文になっていった。
平安朝の陰陽師はまだしも役人ですが、時代が下るとまったくお役所と関係ないような場所や願い事のお札にも「急急如律令」が書かれたりしています。
そもそもの意味を離れ、その言葉自体に呪力があると信じられていたのでしょう。
つまり、人が魅力だったりパワーを感じたりすることばには、そこに「魔法」「ラッキー」が存在しうるのではないか。
その言葉に魅力を感じるのなら、その言葉のパワーを信じられるなら、好きな歌の歌詞だって、小説の一節だって、推しの決めゼリフだって、ネットでふと見かけて心に残ったフレーズだって、魔法の呪文になるはず。
そういえば
「飼い猫が家出して戻ってこない時は
立ち別れいなばの山の峰に生ふる まつとしきかば今帰り来む
という和歌を紙に書いて貼っておくと猫が帰ってくる」
なんていうおまじないもありました。
言葉にはことだまがある。
自分が好きな、自分の気持ちの上がる言葉を自分のラッキーの呪文にするのもアリじゃないでしょうか。
ちちんぷいぷい!でも、
サラガドーラメチカブーラビビデバビデブー!でも、
恋の呪文はスキトキメキキス!でも、
お好きな呪文を唱えて楽しい土曜日を!
*** *** ***
素敵な呪文、わたしも心で唱えてみようっと。みなさまもぜひご一緒に!
来週は、思い切ってふだんのコンフォートゾーンを出て、秘境パワフル神域へお参りしてきたテルミライト花さんのお話です。
どうぞおたのしみに。それではまた来週♪