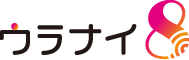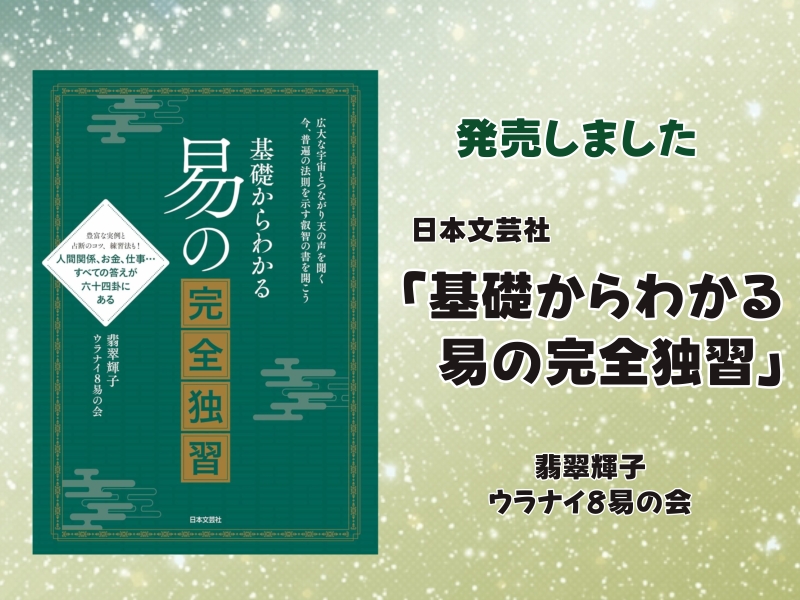占い師の役割は依頼者の人生の物語を語ること。いかに混沌として悩み多き人生でも、物語にできれば生きる力が湧いてくるから。
死後10年たって「再発見」されたアメリカの女性作家ルシア・ベルリンは「わたしはどんな悲惨なことでも笑い話にしてしまえるのなら平気で話す」と書いています。
なにしろルシア・ベルリンの人生はあまりにも濃密です。
1936年アラスカに生まれ、鉱山技師の父の仕事のためアイダホ、ケンタッキー、モンタナを転々とし、父が太平洋戦争に出生するとはテキサス州エルパソの母の実家に移住。戦後はチリに移住し、大学進学でアメリカへ。20代から創作を始め、結婚と離婚は各2回。子供は男の子が4人。教師、掃除婦、電話交換手、ERの看護師などさまざまな仕事をする。アルコール依存症になり克服、大学や刑務所で創作を教え、68歳の誕生日に死去。
たった一人でこれだけの盛り沢山! まるで何人もの人生w凝縮したかのようです。
いくら波乱万丈の人生を送ったからといって、そのまま文字に起こしたのでは物語にはなりません。ルシア・ベルリンの創作形式はオートフィクションの呼ばれ、実体験を取捨選択して語り直すという手法です。息子の一人はこう語っています。
我が家の逸話や思い出話は徐々に改変され、しまいにはどれが本当のできごとだったかわからなくなった。それでもいいとルシアは言った。物語(ストーリー)こそすべてなのだからと。
本当のできごとなんて、誰も正確に表現はできません。時間が過ぎればさらにあやふやになっていきます。しかし、起こったことが自分にとってどういう意味を持つのかが理解できないと生きるのが困難になります。
ルシア・ベルリンは作家としての野心は希薄で、とにかく書くことで苦難に満ちた人生を乗り切りました。
『掃除婦のための手引書』には、刑務所での作文教室を題材にした一編もあります。受刑者たちが与えられた課題に応じて物語を書くことで自分の人生の意味を再確認していくプロセスは感動的です。
占い師と言えば「だまって座ればぴたりと当たる」のが一番すごいと思われがちですが、過去に何があったかを言い当てられても、それが生きる糧になるでしょうか。はずしてもいいし、脚色があってもいいと私は思います。依頼者が「それこそ私の物語だ」と感じられたら、その占いは成功です。